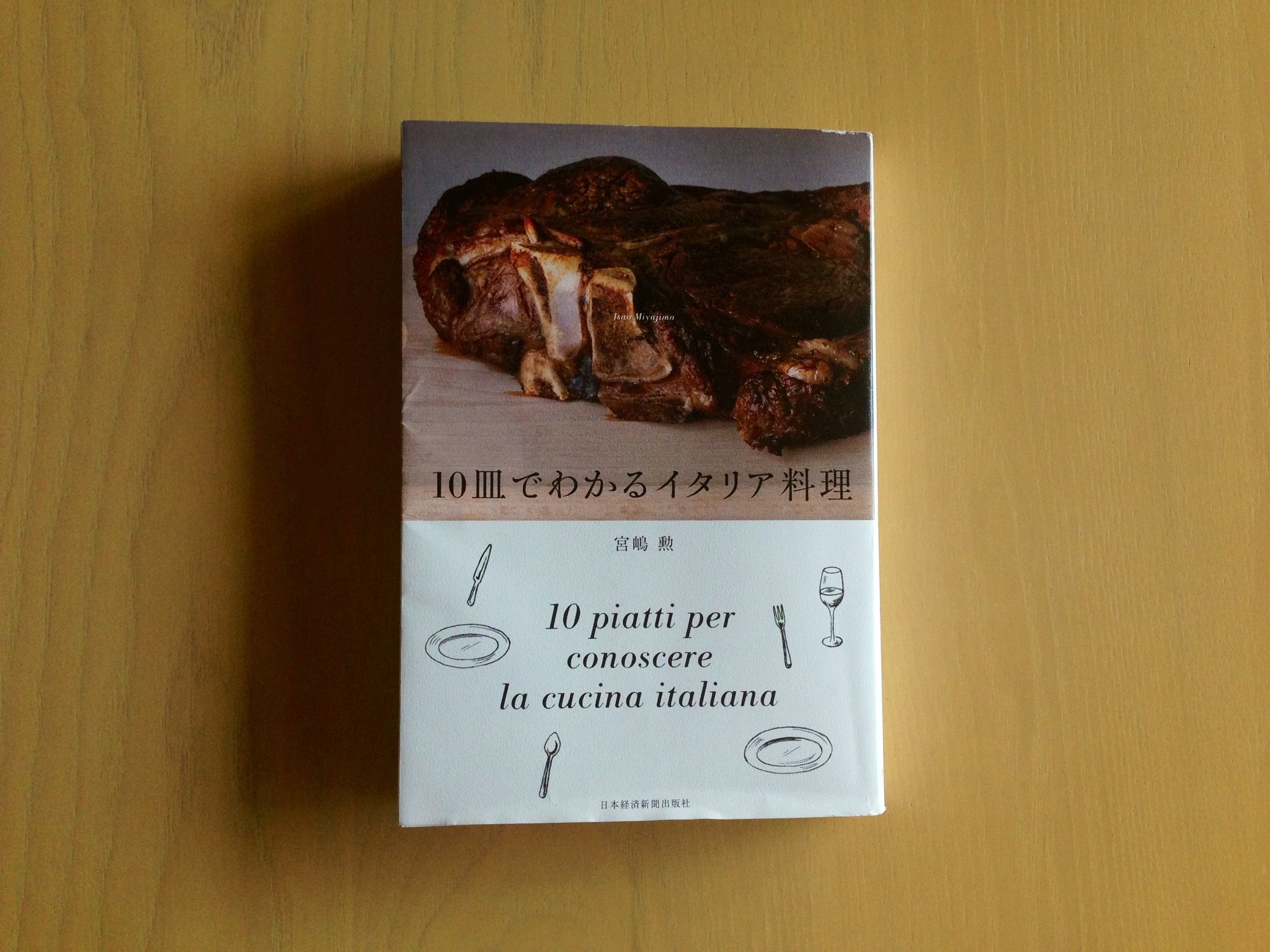このところ、”整体”にハマっている(正確に言うと、そこの整体師にハマっている…笑)。
この暑さのせいか、眠りも浅く、肩こりもひどく、マッサージを時々してもらっても、その時は気持ちがいいけど、すぐにまた同じ状態に戻ることを繰り返しているので、何か他に手はないものかと考えていた。
そこで行われる整体は、強い力でバキバキ音を鳴らすような整体ではなく、手足や関節を揺らしながら、筋肉の緊張をとってゆくやり方。
“ひどい肩こりは、単純な筋肉の疲労ではなく、自律神経が弱り、自分で回復する力が落ちているということです。 そのような肩こりは、自律神経を整え、体を内側から緩めていく整体が適しています。からだは外部からの強い刺激には身構えて抵抗しますが、やわらかい優しい刺激は素直に受け入れます。”
『なんだ、問題は、肩こりだけでなく、自律神経が弱っていたのか!』
そんな考えに導かれたのと、キックボクサーで元全日本チャンピオンという院長のプロフィールとやさしげな顔写真に惹かれ、試してみようと行ったのが始まり。
自分の症状を説明しながら、整体の時間は30分くらいだけど、関節を揺らされながら緊張がほどけていくのがわかる。
僕は今、左肩を痛めているのだけど、そんな相談も、自分の怪我歴から丁寧にお話してくれる。
最後に頭蓋骨の整体をやるのだけど、頭蓋骨の収縮する動きに合わせて先生の両手に包まれているだけで、どうかこのまま、この時間がいつまでも続きますように…と思いながら、うとうと眠ってしまう。
まるで”北風と太陽”のように、気持ちいいということに、からだは自然に反応しているのがわかる。
今日も帰り際、やさしい顔を見ながら、「また来週来ますね!」と元気よく言ってしまった…
この暑さのせいか、眠りも浅く、肩こりもひどく、マッサージを時々してもらっても、その時は気持ちがいいけど、すぐにまた同じ状態に戻ることを繰り返しているので、何か他に手はないものかと考えていた。
そこで行われる整体は、強い力でバキバキ音を鳴らすような整体ではなく、手足や関節を揺らしながら、筋肉の緊張をとってゆくやり方。
“ひどい肩こりは、単純な筋肉の疲労ではなく、自律神経が弱り、自分で回復する力が落ちているということです。 そのような肩こりは、自律神経を整え、体を内側から緩めていく整体が適しています。からだは外部からの強い刺激には身構えて抵抗しますが、やわらかい優しい刺激は素直に受け入れます。”
『なんだ、問題は、肩こりだけでなく、自律神経が弱っていたのか!』
そんな考えに導かれたのと、キックボクサーで元全日本チャンピオンという院長のプロフィールとやさしげな顔写真に惹かれ、試してみようと行ったのが始まり。
自分の症状を説明しながら、整体の時間は30分くらいだけど、関節を揺らされながら緊張がほどけていくのがわかる。
僕は今、左肩を痛めているのだけど、そんな相談も、自分の怪我歴から丁寧にお話してくれる。
最後に頭蓋骨の整体をやるのだけど、頭蓋骨の収縮する動きに合わせて先生の両手に包まれているだけで、どうかこのまま、この時間がいつまでも続きますように…と思いながら、うとうと眠ってしまう。
まるで”北風と太陽”のように、気持ちいいということに、からだは自然に反応しているのがわかる。
今日も帰り際、やさしい顔を見ながら、「また来週来ますね!」と元気よく言ってしまった…